今回は、1977年に発表されたチープ・トリックのセカンドアルバム『In Color(邦題:蒼ざめたハイウェイ)』に収録された「Big Eyes」という曲に焦点を当ててみるばい。
この曲に隠された深い意味や、アート界の異端児マーガレット・キーンの“大きな目”の絵との関係、そして映画監督ティム・バートンの美学と絡めて、独自の考察を書いてみるけん、音楽ファンや映画ファン、アート好きの方にもおおっ!て思ってくれたら嬉しかばい。
それは、たまたまチープ・トリックの「Big Eyes」のイントロを爪弾いていた時やった。
外は35度のあっつい気温。
エアコンの効いた午後の部屋で、ふと手に取ったギター。
何気なく弦に触れた瞬間、あの印象的なリフが指先からこぼれ落ちてきた。(詩的やろ??)
──Big eyes / I keep falling for those…
コードの響きが空気を震わせたとき、不意に、あの“大きな目”の絵が頭をよぎった。
そう、マーガレット・キーンの、悲しげで、どこか訴えかけるような子どもたちの瞳。
「…もしかして、この曲って、あの目のことを歌っとるんじゃなかろうか?」
そんな妄想めいた連想から始まった。
けれど、調べれば調べるほど、「Big Eyes」はただのラブソングには収まらん深みを持っとることに気づいたったい。
1977年、チープ・トリックのセカンド・アルバム『In Color(邦題:蒼ざめたハイウェイ)』に収録されたこの曲は、シンプルながらもクセになるリフと、ロビン・ザンダーの艶っぽいボーカルが印象的やけど、それ以上に、詞の裏にある“見る”という行為、あるいは“見られる”ことへの無意識の欲望が浮かび上がってくる気がしてならん。
マーガレット・キーンの描く大きな目。
それは少女たちの無垢と孤独を象徴しとると言われるけど、同時に、他人の感情を吸い取る“窓”のようでもある。
1960年代アメリカのリビングを席巻したその絵は、“大衆芸術”として揶揄されもしたが、多くの人がそこに心を奪われたっちゃんね。
音の特徴
- ミッドテンポでブルージーなギターリフが印象的。
- ロビン・ザンダーのボーカルはねっとりとセクシーで、同時にどこか狂気を感じさせる。
- ドラムとベースはしっかりと曲の土台を支え、全体的にダークで重厚な雰囲気を作り出しとる。
歌詞はシンプルやけど奥が深かと。
“Big eyes, I keep falling for you”というフレーズを軸に、「大きな目に惹かれてしまう」一方で、「君の言うことは嘘かもしれん」という不信感も表現されとる。
これは単なる恋愛ソング以上の、見つめることと見られることの葛藤を示唆しとるっちゃんね。
・歌詞冒頭部分
It’s not the way you look no-no
It’s not the way you walk
Your eyes are somethin’ good
You know they’re clear and bright
It’s not the color of your hair
ここで強調されとるのは、外見の表面的な要素(顔立ち、歩き方、髪の色)ではなく、「目」だけが特別な存在として抜きんでてるばい。
これは単なる「目が大きいから好き」っていうこと以上に、**目が「魂の窓」や「真実を映す鏡」**として認識されとる証拠ばい。
・フレーズの意味
Big eyes
I keep falling for those
Big eyes
They keep calling my name
この「Big eyes」は魅力的なだけじゃなく、引き寄せられ、逃げられない運命のようなものとして描かれとる。
「目が呼びかける」という表現は、相手の目が何か強烈なメッセージを伝え、見つめる側の心を操っとる感じがあるばい。
ここに「見られることと見つめることの主従関係の曖昧さ」や、「逃れられない視線の魔力」が潜んどる。
急展開の部分
You’re such a losin’ cause
Who says you write the laws
Why don’t you go get lost
Who says you write the laws
Go on get out of here
この部分は、急に攻撃的で反抗的なトーンに変わるばい。
これは、相手に対する怒りや拒絶の感情を表しとる。
「法律を書いてるわけじゃないんやろ?好き勝手しやんな」という反発は、関係の中の葛藤やコントロールされることへの反抗を示しとるっちゃね。
歌詞ば整理してみる。
歌詞の最初では、目に魅了されていく過程が描かれとる。
相手の「大きな目」に惹かれて、どんどん深みにはまっていく感じ。
でも、次第にその魅力が過剰になり、 支配されているような不安や反発が生まれるとる。
目の魅力にはとても強い力があるけど、それが「呼びかける」と感じるとき、相手が自分をコントロールしているように思えてくる。
その反動として、急に 反発心 が湧いてくる。「何でお前がルールを決めるんだ?」みたいな怒りが出てきたんじゃないかと。
「Who says you write the laws」というフレーズが反抗的な理由は、相手に対しての力関係の逆転を試みる表現やけん。
最初はその魅力に引き寄せられ、支配されそうな自分があったけど、そこから「お前のルールで動かされるのは嫌だ」っていう気持ちが強くなってきた。これは、相手に コントロールされることへの抵抗であり、自分の意志を取り戻すための反抗とも取れる。
この急な反抗的なフレーズは、単に恋愛の中での感情のアップダウンを示すだけじゃなくて、個人としての尊厳や自由を守りたいという気持ちが浮き彫りになっとる。
もしかしたら、最初は「大きな目」に魅了されていたけど、だんだんその目が自分を押さえつけているように感じ、それに対して 反発心が芽生えたという流れがあったのかもしれん。
「Go on get out of here」っていうフレーズが、ここで相手に対しての怒りや軽蔑を表現していると考えると、すごく強いメッセージやん。
これは単なる恋愛のひとときの感情じゃなくて、自分を取り戻すための叫びのように感じられるばい。
たかが歌詞と思っとったけど、ここまで深いとは、恐るべしばい!!
・マーガレット・キーンの“大きな目”の絵と「Big Eyes」
ここで、マーガレット・キーンの話をせんといかん。
彼女は1960年代に人気を博したアメリカの画家で、特に「ビッグ・アイズ」と呼ばれる特徴的な大きな瞳を持つ子どもや動物の絵で知られとる。
この大きな目は、単なるデフォルメやなくて、感情や孤独、哀愁を深く表現するための窓になっとるっちゃね。
見る者にじっと見つめ返し、時には見透かされるような感覚を与える。
実はマーガレットの夫が彼女の絵を自分の名で売り、長年隠蔽されとったという物語は2014年にティム・バートンによって映画『ビッグ・アイズ』として描かれたっちゃんね。
共通する視覚的モチーフ
チープ・トリックの「Big Eyes」とキーンの絵は、共に“目”が持つ圧倒的な力をテーマにしとる。
大きな目はただの可愛さや美しさじゃなく、見る者を引き込み、時に不安や狂気を感じさせる不思議な魅力があるっちゃん。
・ティム・バートンの美学
ティム・バートンはポップカルチャー界の異端児で、作品全体に**「ポップ×ダーク」**のバランス感覚が溢れとる監督ばい。
彼の代表作には『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』や『ビートルジュース』、そして『ビッグ・アイズ』などがある。
ティム・バートン美学のポイント
- ポップでキッチュながら、不気味さや哀愁を隠さない。
- アウトサイダーの視点を大事にし、変人や孤独者を主人公に据える。
- ユーモアと狂気のギリギリのバランスをとることで、怖くも愛おしい世界観を作る。
- 子どもの無垢な視点と大人の絶望が同居する。
- 美術的に細部までこだわる独特のアートスタイルを持つ。
チープトリックとティム・バートンの共通点
チープ・トリックはキャッチーで聴きやすい曲調が多いけど、その中には不安や狂気、皮肉や哀しみがしっかり潜んどる。
バートンの映画も同様に、色鮮やかで楽しい世界観の中に毒と切なさを込めとるばい。
アウトサイダーの肯定
どちらも「普通じゃない」キャラクターや表現を肯定し、むしろそれを武器にしとる。
チープ・トリックのリック・ニールセンは、オタクっぽい見た目や個性を隠さずに逆手に取っとるし、バートンも変人や孤独者を主役に据える。
ユーモアと狂気の共存
笑わせながら怖がらせる、その微妙なバランスを保つのが両者の得意技。
これが見る者・聴く者の心を掴んで離さないんよね。
俺的なまとめ
チープ・トリックの「Big Eyes」、マーガレット・キーンの絵、ティム・バートンの映画は、単なる偶然の一致じゃなかと思う。
それぞれがアメリカ文化の「ポップ×ダーク」「キッチュ×哀愁」の交差点に立ち、見る者の感情を揺さぶり続けとる。
「Big Eyes」は、単なる目の大きな女の子の歌やなく、“見ること、見られること”の葛藤や恐怖、魅力を詰め込んだ深い曲やけん、
このテーマを理解すると、曲の聞こえ方がぜんぜん変わってくるばい。
どげんね?


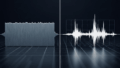

コメント