映画を“切る”より、“拾う”ということ
――つくる人間としての感想
「ジュラシック・ワールド/復活の大地」に“今年の駄作決定!”なんて感想を見かけて、正直、残念な気持ちになったばい。
もちろん、映画の感想は人それぞれ。
好き嫌いがあるのは当然やし、批判も作品の受容のひとつやと思う。
でも、俺はものをつくる側の人間やけん、どんな作品にも“ちょっとでも良いところ”を見つけてあげたいんよね。
それが、つくった人への敬意でもあるし、自分自身の創作にもつながると思っとる。
映画って、“好き”とか“嫌い”だけじゃ語れんことが多か。
それよりも、“その人に合うかどうか”っていう表現のほうが、ずっと誠実やと思うっちゃん。
ある人には退屈でも、別の誰かには心に残る一作になる。
だからこそ、俺はどんな作品にも「ちょっとでも良いところ」を見つけてあげたかっちゃんね。
駄作って言葉は、簡単に口にできる。
でもその裏には、何百人、何千人が関わって積み上げた時間と情熱がある。
脚本、演出、美術、衣装、音響、編集・・・どれかひとつでも欠けたら、映画は完成せん。
たとえ物語が荒削りでも、演技が浮いてても、「この一瞬のカットは美しかった」とか「この音楽の入り方は絶妙だった」とか、 そういう“光る断片”を見つけるのが、俺にとっての映画を見る、ことなんよ。
ジュラシック・ワールドの最新作も、たしかに賛否はある。
でも、水中を泳ぐTレックスのシーンを観たとき、「これは今の技術じゃないと絶対にできんかった」っちゅう記事ば読んどったけん、かなり期待してワクワクしながら見てしもうたばい。
ほんと迫力会ったと思う。
水の揺らぎ、皮膚の質感、光の屈折——あれはCGの粋と演出の挑戦が詰まっとる。 ただの“恐竜出ました”じゃなくて、“恐竜が生きてる”って感じさせる一瞬。
それを「つまらん」のひとことで切り捨てるのは、ほんと惜しかったい。
映画って、技術と物語が融合する芸術やけん、時代によって“できること”が変わってくる。
たとえばくさ・・・
- 『アバター』では、顔の筋肉まで拾うパフォーマンスキャプチャで、CGキャラが“生きた存在”になった。
- 『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』では、ブラッド・ピットの若返りをCGで自然に描いて、時間の流れを身体で感じさせた。
- 『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』のデイヴィ・ジョーンズは、触手の動きまで演技に昇華させたCGキャラの革命。
- 『トロン:レガシー』では、光と空間の演出が3Dで没入感を生み、“現実じゃない世界をリアルに感じる”体験ができた。
- 『マトリックス』のバレットタイムは、“時間を操る”映像表現の先駆けとして、今も語り継がれとる。
こういう技術って、単なる“すごい映像”じゃなくて、物語の説得力や感情の深さを支える土台になっとるんよね。
そしてそれは、観る側が“拾う視点”を持ってこそ、ちゃんと届くものやと思うとよ。俺は、作品を“切る”より、“拾う”ほうが好きやけん。
そのほうが、つくった人の気持ちにも、観た自分の気持ちにも、優しくなれる気がする。
たとえ全体が荒削りでも、「この一瞬は美しかった」「この音は心に残った」って言えるほうが、 自分の創作にも、次の鑑賞にも、きっといい影響を与えてくれると思うったい。次に映画を観るとき、ちょっとだけ“良かったところ”を探してみてほしかばい。
それは、つくった人への敬意でもあり、自分自身の感性を育てることにもなるけん。
映画って、合う/合わんはあって当然。
でも、そこに込められた誰かの努力や誇りは、きっとどこかに光っとる。
それを見つけるのが、俺にとっての映画を見る、ってことなんよ。

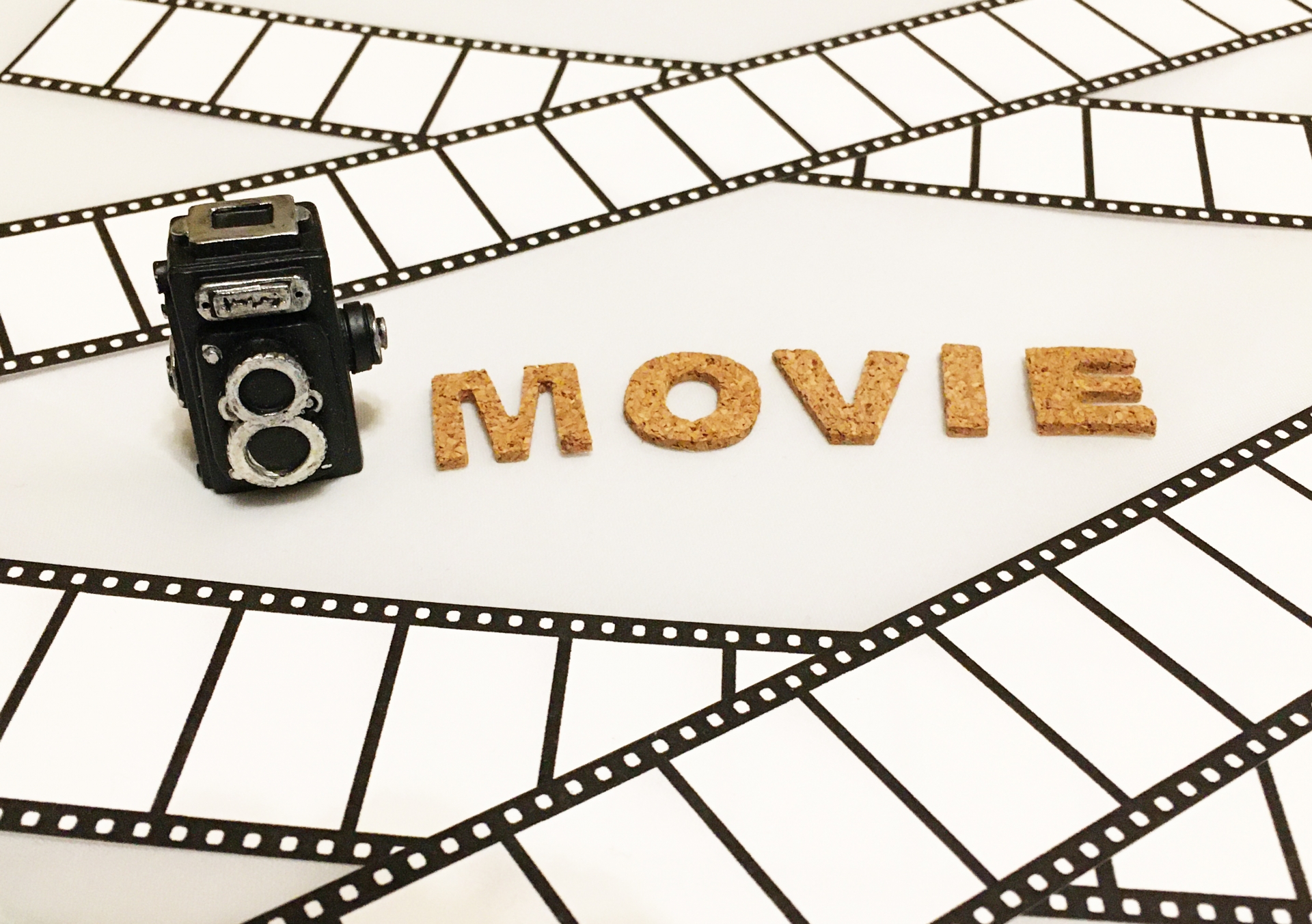


コメント